
飲んでる酒・読んでる本・聞いてる音楽が全部お洒落な 我妻許史 さんにエピソードを頂きました!
我妻許史 さんのブログ(誌)的ライナーノーツ はこちら
俺の宗教はニルヴァーナだった。
行動規範はカードコバーン。自己憎悪と破壊衝動を身体の中心に据えて渋谷や下北沢で暴れ回っていた。
バカだった。バカだったし、不幸だった。暴力が得意そうなお兄さんに囲まれてサッカーボールになったこともあるし、トラックの運ちゃんと揉めて轢き殺されそうになったこともある。それでも俺は、「これぞパンクロック」と嘯いて、にやにや笑っていたんだから救いがない。
ある日Nさんに、イベントに出演しないか? と誘われた俺たちは、決起集会と称して渋谷の飲み屋に集まった。クソほど退屈だった。四、五組のバンドが集まって「いいイベントにしよう」と口では言っていたけど、そこにいる全員が、自分たち以外のバンドを見下していたに違いない。
「くだらねえからやっちまうか?」
メンバーがラジカルな発言をし、俺も、そうだな、そろそろ暴れなくちゃな……と立ち上がり、ビールケースを二階から一階へぶん投げた。
主催のNさんはとても困った顔をしていた。Nさんは(´・_・`)こんな顔をして「なんで……」とつぶやいた。そう、彼はバンドマンでは珍しい「いい人」だった。
俺は喧嘩になると思っていた。だけど、そんな雰囲気にはならず、場は静かに冷えていた。俺も素になっていた。「なんでこんなことしたの?」と自分に問いかけた。「自分、なんでそんなことしたん?」と関西弁でも問うた。続けて「そんなことしたらアカンやろ?」と問い、全俺の中で始まった会議で答えが出た。
答:アカン
俺はカート教を脱会した。
いつの間にか俺はカート・コバーンが死んだ年を超えていた。
酒=パンクロックだった季節は過ぎて、俺は酒を仕事にするようになった。
汐留の酒屋の副店長、ワイン担当だった俺は、電通や日テレなどで働く上級国民にワインを売っていた。
そこそこ売上がいい店で、インポーターの営業がほぼ毎日、店に来た。
「これ飲んでください。そして気に入ったら仕入れてください」というわけだ。
タダ酒はハッピーなんだけど、度を過ぎると不幸の種になる。
問題はいつ飲むか? だった。仕入れ担当だから、仕事中でも飲むことはできる。だけど、物事はそう簡単じゃない。接客がある。事務作業がある。アルコールで痺れた脳で仕事をしたら、あじゃぱーになってしまう。そのころは「仕事中にあじゃぱーはちょっとね……」と思えるぐらいの社会性を身につけていたから、試飲は閉店後に行った。
会社の飲み会を憎悪する、人付き合いが悪い俺は誰よりも早く家に帰りたかった。仕事が終わってから仕事の話をするのは嫌だったし、仕事が終わったあとに仕事のことを考えたくなかった。
当時の上司は俺と真逆な性質をもっていて、仕事後もワインの話をしたかったし、家に帰りたくないタイプだった。
上司はあの手この手を使って、俺を終電に間に合わせない努力をした。俺はその策略にハマり、月に二度は終電を逃した。
俺のデスクには常に抜栓前のワインが並んでいて、俺に飲まれるのを待っていた。
ワインの資格取得のために勉強をしていたときも、ミシュランフレンチでソムリエをしていたときも、新橋でワインの営業をしていたときも、ずいぶん過度に飲酒をしていたけど、このときほどハードには飲んでいなかった。
試飲サンプルだから一口だけ飲んで残りは捨ててしまってもいいんだけど、小市民の俺はどうしてもそれができず、毎日きっちり二本か三本飲み干してから職場を後にした。
その日もしっかり飲んでいた。カバのようにのっそり動く上司を置き去りにして、ワインの空瓶をゴミ捨て場に捨てた俺は汐留駅に走り、電車に飛び乗った。
帰るパターンは二パターンあり、新宿で乗り換えるパターンか、東中野で乗り換えるかのどちらかだった。車内が混雑しているときは、新宿で乗り換え、座れるときは、新宿で降りずに東中野まで、というのが俺のルールで、その日は座ることができた。つまり、東中野ルートだった。
「起きてください!」
乱暴に肩を揺らされて俺は目を開けた。
駅員に起こされた俺は( ゚д゚)こういう顔をしていたに違いない。着いたのは光が丘、終点だった。
車内を見回すと俺のほかにも( ゚д゚)こんな顔をしているやつがいた。
俺( ゚д゚)と、少年( ゚д゚)は、慌ただしく車内を追い出され、殺風景な場所に取り残された。
俺と少年はアイコンタクトを取った。
( ゚д゚) ココドコ?
( ゚д゚) シラン
俺たちは歩み寄り、テレパシーから人間が扱う言語に切り替えた。
「寝過ごしたわ」
「兄さんも乗り過ごした感じすか?」
「きみも?」
「はい……」
俺と少年は動物園の熊のように、のそのそと駅周辺を歩き、腹を掻いて、空を見上げ、猿のダンスを踊り、ため息をついた。状況を整理するのに五分かかった。とにかくここにいてもしょうがない。光が丘という名前は素敵だけど、ひとつも光ってる要素はなかった。
「きみん家は近い?」
俺は少年に訊いた。
「要町っす」
「どこそれ?」
「池袋のほうっすね。兄さんは?」
「俺は西荻窪。杉並だね」
「どこっすか?」
俺たちは地図アプリを見て現在地を確認した。少年の家のほうが俺ん家よりも若干近いということがわかった。
「いくら持ってる?」
俺は少年に訊いた。少年は財布から千円札を二枚抜いて「これだけっすね」と言った。
「少ねえな。俺はもうちょいあるはず……」
俺の所持金は三千円だった。
「あのさ、五千円あったらタクシーで要町まで行けないかな? 悪いけどさ、今日泊めてよ」
「いっすよ。じゃあ、俺タクシー拾ってきます」
少年は元気よく、タクシー乗り場に突撃し、「五千円で要町まで行けますか?」と訊いて回った。
答えは「アホか」だった。
何人かの運転手に訊ねて回り、昔はヤンチャしてた感のある運転手に、「お、お前ら青春やんけ! そんなら五千円で乗せてったるわ」と言われ、その行為に甘えることにした。俺たちはその場で感謝の舞を踊り、車内に乗り込んだ。
少年の家はファンシーだった。大学生の一人暮らしなのに、割としっかり目の戸棚があり、その中にはロイヤル・コペンハーゲン風のカップとソーサーが並んでいた。
「ポカリ飲みます?」と言われ、俺は「うん」と言った。少年は、部屋を出て冷蔵庫からポカリスウェットのペットボトルを持ってきて、コペンハーゲン風のカップに注いで俺に手渡した。一口で飲み干した俺は「もっと飲みたいな」と思ったけど、少年はペットボトルを戻しにいっていた。普通のグラスとかないんかいと思ったけど、思うだけで口にはしなかった。
俺と少年は海外サッカーの話で盛り上がった。一時間以上、白熱のフットボールトークを展開し、一瞬の間が空いた瞬間、少年は寂しそうな顔をした。
「……俺、就活うまくいってないんすよ」
と少年は言った。
俺は「うん、うん」という顔をしながらも、やだな、と思った。そんな話すんなよ、と思った。ポカリもっともってこいよ、と思った。だけど、俺は少年の苦悩を受け止め、あまつさえ、就活のアドバイスをした。俺は就活なんかしたことないのに。
少年の瞳は徐々に輝きを取り戻し、俺たちはルイス・フィーゴのドリブルや、アイマールの閃きについての話に戻っていった。
気づいたら朝だった。起きた瞬間ヤバいと思った。なぜ、遅刻するときは、時計を見る前からわかるんだろう、と思ったけど、そんなことを分析する余裕がないぐらいヤバいと思った。
俺は自分の荷物をまとめて、家を出る準備をした。少年はぐっすり寝ていた。俺は履いていた靴下を洗濯機に入れ、彼のタンスを漁って、黒い靴下に履き替えた。そして冷蔵庫からポカリを出してその場で一気飲みした。
家を出ると、見知らぬ街の光が容赦なく俺に降り注いでいた。
店に着くと、俺のデスクの上には新しいワインが何本も並んでいた。
ここまで書いて、もしかして俺は酒で失敗したことはないんじゃないか? と思った。きっと俺は人生に失敗してるだけなんだ。
それは、ものを考えない浅はかさと、思慮の足りなさ。渚にまつわるエトセトラ。干支は犬。
か弱い葦のような存在の人間は、ものを考えることができるから現在も地球の覇者として君臨することができる。それを放棄して生きてきた俺は葦の茎以下の存在だった。
考えようぜ。考えて飲むんだよ。
それを知るのに十年以上かかったけど、その甲斐はあった。
今の俺は、パンセに敬礼することもできるし、コーヒー色したペリカンの話をしてあげることもできる。ロベルト・ボラーニョの著作について講釈を垂れることもできるし、その日の気分に合わせてワインを選ぶことができる。それって素敵なことじゃないか?
今日、久々に少年のインスタグラムを見た。少年はすでに逞しい青年となり、現在、出版社で働いている。
最新の投稿はこうだ。
「入籍!」
彼は奥さんと二人で婚姻届を誇らしげに掲げていた。
ハレルヤ!って感じだ。
俺はいつか、黒い靴下とポカリ一リットルの借りを返そうと思っている。
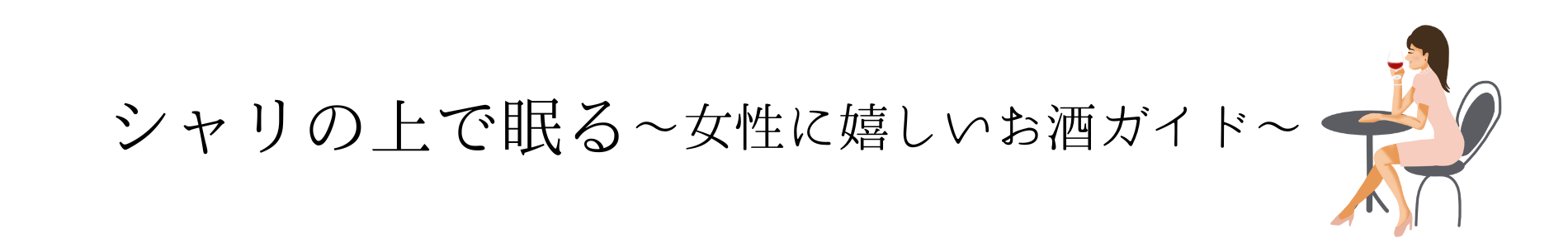



コメント