

こんにちは!麦芽(ばくが)のことをムギメと読んでいたおさしみです。今までの人生で「麦芽!」と人前で発言する機会が無くて本当に良かった。
さて、みなさんはビールと発泡酒の違いを知っていますか?
多くの人が「ビールより薄くて安いのが発泡酒?」という漠然とした認識を持っていると思います。
かくいう私も麦芽をムギメと読んでいたくらいですので全く知識がありませんでした。
ビールと発泡酒は見た目や味わいが似ているため、初心者には区別が難しいかもしれません。ですが、これらには原料や価格などが異なっており明確に違いがあるのです。
この記事では、ビールと発泡酒の違いについてわかりやすく解説していきます!
そもそもビール・発泡酒とは

ビールの定義
国税庁の「ビール・発泡酒に関するもの」という項目に下記の記載があります。
ビールは、A 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合100%)及びB 麦芽、ホップ、水及び麦、米や果実、コリアンダーなどの香味料等の特定の副原料を使用して発酵させたもので、麦芽の使用割合が50%以上のものをいいます。
引用:国税庁サイトより
まとめるとビールは
A 「麦芽、ホップ、水」を原料とした麦芽の使用割合100%のもの
B 「麦芽、ホップ、水」の他に副原料を使用した麦芽の使用割合が50%以上のもの
ということです。
色々書いてありますが、ここで発泡酒との比較時にポイントとなるのは
・麦芽の使用割合が50%以上のもの
・特定の副原料を使用しているもの
という箇所です。
発泡酒の定義
同じく下記は国税庁の「ビール・発泡酒に関するもの」の記載です。
発泡酒は、麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある酒類で、具体的には、A 麦芽の使用割合が50%未満のもの、B ビールの製造に認められない原料を使用したもの、C 麦芽を使用せず麦を原料の一部としたものが該当します。
引用:国税庁サイトより
なお、発泡酒については麦芽の使用割合により税率が3分類に区分されています。
まとめると発泡酒は
A 麦芽の使用割合が50%未満のもの
B ビールの製造に認められない原料を使用したもの
C 麦芽を使用せず麦を原料の一部としたもの
だそうです。
こちらも色々書いてありますが、ビールとの比較でポイントになる箇所は
・麦芽の使用割合が50%未満のもの
・ビールの製造に認められない原料を使用したもの
という部分です。
これらのポイントについてもう少し詳しく解説していきます。
原料の違い

麦芽の使用割合が50%以上か未満か
ビール・発泡酒の定義で麦芽の使用割合という聞き慣れない言葉が出てきました。
「麦芽」とか「割合」とか言われると難しく思いがちですが、麦芽の使用割合とはその名の通りビールの主な原料である麦芽、ホップ、水のうち麦芽が占めている割合を指します。
麦芽の使用割合…ビールの原料となる麦芽がどのくらい使われているかを表す割合のこと
この麦芽の使用割合が50%以上であればビール、それ未満であれば発泡酒となります。これがビールと発泡酒の大きな違いです。
麦芽の使用割合が50%以上であればビール
麦芽の使用割合が50%未満であれば発泡酒*
*麦芽の使用割合が50%以上でも発泡酒となる場合があります。詳細は次の項目へ。
認められている副原料を使っているか
ビールの主な原料は麦芽、ホップ、水ですが、その他にも副原料としてさまざまな原料の使用が許可されています。
言い換えると、ビールは使用が許可されている副原料以外使うことはできません。
副原料…ビール製造において使用が許可された原料のこと(ばれいしょ、とうもろこし、コリアンダーなど)
ビール製造で認められている副原料はこちらです↓(引用:平成 29 年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A)
麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類又は一定の苦味料若しくは着色料
果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮した果汁を含む。)
コリアンダー又はその種
ビールに香り又は味を付けるために使用する次の物品
・ こしょう、シナモン、クローブ、さんしょうその他の香辛料又はその原料
・ カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
・ かんしょ、かぼちゃその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
・ そば又はごま
・ 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
・ 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
・ かき、こんぶ、わかめ又はかつお節
これらの副原料を使っていればビール、これらの副原料以外の原料を使っていれば発泡酒、
副原料を使用していればビール
副原料以外の原料を使用していれば発泡酒
と言いたいのですが、、、
副原料にはさらに「麦芽の量に対して5%を超えてはいけない」という決まりがあるんです。
ちょっとややこしいですが副原料に関してはこのようになります。
副原料(麦芽の重量の5%以内の場合)を使用していればビール
副原料(麦芽の重量の5%を超える場合)を使用していれば発泡酒
副原料以外の原料を使用していれば発泡酒
また、さきほど説明した麦芽の使用割合50%以上のものでも副原料のルールを守っていなければ発泡酒となります。
原料の違いについてまとめ
【麦芽の使用割合】
・50%以上であればビール
・50%以下であれば発泡酒
【副原料】
・麦芽の重量の5%以内の量を使用していればビール
・使用していなければ発泡酒(1)
・麦芽の重量の5%を超える量を使用していれば発泡酒(2)
【その他】
麦芽の使用割合50%以上でも(1),(2)に該当していれば発泡酒
値段の違い

次に誰もが気になる価格の違いについて。
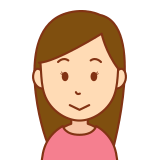
ビールは発泡酒より高い!
という認識。実は合っているようで間違っているんです…!
お酒にかかる税金、酒税は「ビールか発泡酒か」で決まるのではありません。
「麦芽の使用割合」によって決まります。
なので
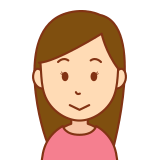
麦芽比率50%のお酒は麦芽比率50%未満のお酒より高い!
というのが正しいです。それでは解説していきます。
酒税に関係するのは「ビールか発泡酒か」ではない
国税庁が公表している「酒税率一覧表」に1㎘当たりの税率が提示されています。

350㎖(缶一本分)の酒税を出すとこうなります。
| 分類 | 計算 | 350㎖あたりの酒税 |
| ビール | 200,000÷1,000,000×350=70 | 70円 |
| 発泡酒(麦芽比率50%以上) | 200,000÷1,000,000×350=70 | 70円 |
| 発泡酒(麦芽比率25%以上) | 167,125÷1,000,000×350=58.4 | 58円 |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満) | 134,250÷1,000,000×350=46.9 | 47円 |
ビールと麦芽比率50%以上の発泡酒の酒税が同額なのがわかりますね!
酒税は麦芽比率によって変わる
一概に発泡酒がビールより安いとはいえない
上記のことから、酒税は「ビールか発泡酒か」ではなく「麦芽比率50%以上か未満か」というルールで決まっていることが分かりました。
発泡酒は原料の制限が厳しくない分、価格にもばらつきがあるんですね。
もちろん、市場に出回っている発泡酒がビールより安いものが多いというイメージは今でもあります。購入の際はちょっと気にしてみてはいかがでしょうか。
これからはビールは安くなる!?
下記にあるように、今後ビールや発泡酒の税が1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に統一されていくことが決まっています。
ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化します(2020年(令和2年)10月から3段階で実施)。
引用:財務省HP 酒税改正(平成29年度改正)について
ビールや発泡酒が統一して350㎖当たり54.25円になると
| 分類 | 改正後の価格 |
| ビール | 70円→54.25円 |
| 発泡酒(麦芽比率50%以上) | 70円→54.25円 |
| 発泡酒(麦芽比率25%以上) | 58円→54.25円 |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満) | 47円→54.25円 |
ビールと麦芽比率25%以上までの発泡酒は安くなり、麦芽25%未満の発泡酒は高くなるということがいえます。
低価格で楽しめた発泡酒は値上がりしてしまいますが、ビールやその他の発泡酒は値下がりし、もっと身近に楽しめるようになりそうです!
味の違い

ビールの特徴:豊かなコクと深い香り
ビールの特徴は麦芽がもらたす豊かなコクと深い香りです。
法律で定められている「麦芽使用比率50%以上」が大きく関わっていることは一目瞭然ですね。また、ホップからくる苦みや爽快感も特徴的です。
ビールはクラシックな深い味わいを求める方におすすめです。
発泡酒の特徴:軽快な味わいと爽やかな口当たり
発泡酒の特徴は軽くて爽やかな味わいです。
麦芽使用比率が50%以上のものはビールと似た深い味わいやコクを感じることが出来ますが、多くの人が認識している低価格の発泡酒(麦芽使用比率50%以下)は比較的あっさりしていて爽やかな口当たりのものが多いです。
発泡酒はより軽やかで爽快な味わいを求める方におすすめです。
まとめ

それぞれの違いを知って味を楽しもう
本記事ではビールと発泡酒の違いを定義、原料、価格、味の視点から比較してきました。ビールと発泡酒の違いを知ることで、それぞれの味わいをより楽しむことができます。
・クラシックで深みのある味を楽しめるビール
・爽快で軽やかな口当たりの発泡酒
自分の好みに合わせて、両方の魅力を堪能しましょう!
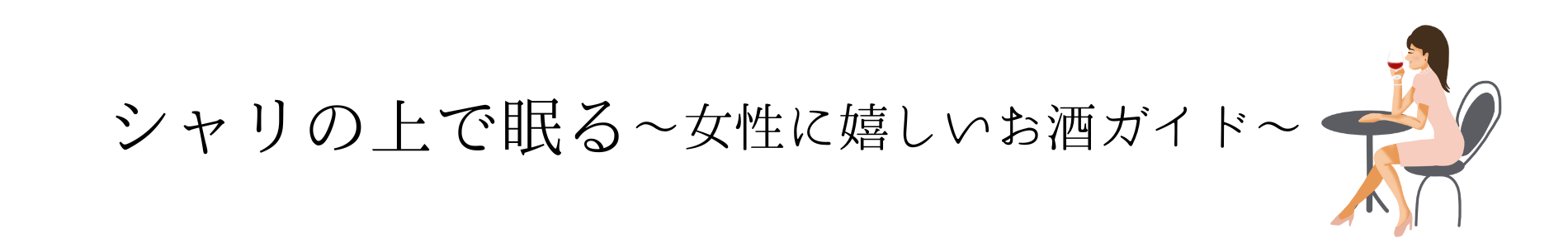





コメント